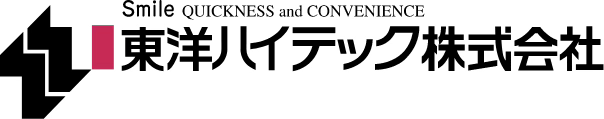東洋ハイテック株式会社
2025/03/28
会社概要・業務内容
社名:東洋ハイテック株式会社
ホームページURL:https://www.toyohi.co.jp/company
所在地:大阪市北区万歳町3-20 北大阪ビル5F
東京支店:東京都中央区東日本橋2-7-1 FRONTIER東日本橋4階
従業員規模:171人
業種:建設業
事業内容:粉粒体設備のプラントエンジニアリング、粉粒体機器・装置の販売
生産性の向上に主眼を置いた“手段”としてのテレワーク
当社では、社員の人生・プライベートの充実が仕事の生産性の向上につながるとの考えに基づき、①「社員の労働時間を減らしたい」、②「仕事と余暇のバランスを大切にしたい」、③「社員に利益還元したい」、④「社員のキャリア形成を充実させたい」の観点から、『働くだけが人生じゃない!』をコンセプトに掲げ、目標の実現に向けた“手段”として、2020年からテレワーク制度を導入しています。
制度導入後は通勤にかかる移動時間などの就労負荷の減少により、社員一人ひとりの生産性は向上し、拠点や居住地に縛られない働き方が可能になったことで、転勤や家庭事情による退職者の減少、社員の地方移住を実現するなど、各方面で一定の成果を上げています。
 地方移住社の所在地
地方移住社の所在地
業務工程を分解・検証し、テレワークに則した働き方を推進
現場での常駐作業がメインとなる建設・エンジニアリング業界では、テレワークの実施は困難と言われてきました。その理由は、特にプラントエンジニアリングの場合、複雑な業務フローが敷かれているため、通常は1つの工程ごとに担当者が分かれていることによります。
一方、当社では長年、1つの案件を同じ社員が担当する「プロジェクト体制」を採用していたため、「設計」→「施工管理」→「最終試運転」までの工程を一気通貫で担ってきたことが、テレワーク導入に成功した要因だと考えています。
当社では、「プロジェクト体制」における各工程を見直し、①見積りや設計図の作成など「テレワークで完結する業務」、②協力会社への訪問など「日帰り~2日程度の外出が必要な業務」、③最終試運転など「数週間~数カ月の常駐が必要な業務」のように、業務内容を分解・検証することで、テレワークが可能な工程かどうかを判断します。これにより、担当社員が現場に出向く頻度や拘束時間を最小限に抑えることができました。
社員の中には、介護や育児により「現場に行けない社員」もいれば、自宅環境の問題で業務に集中できず「現場に行きたい社員」もいます。テレワークを前提とした働き方としつつも、当社では、社員の個々の事情や希望を踏まえたうえで業務分担や配置を行う「分業制」も一部で認めることとしました。「プロジェクト体制」と「分業制」の併用により、社員間の“不公平感”の解消にも繋がっています。
社員間の「意識格差」を埋めるための各種施策を実践
テレワークに対応すべく、現場の担当社員はウェアラブルカメラやTeamsを活用しながら現場の状況を報告します。送られてくる各種データを基に、プロジェクトリーダーは自宅にいながら複数の案件を並行して管理することで、生産性を向上させています。
設計図などの図面についても、かつてはプロジェクトのメンバーが会議室に集まり、紙に出力したものに全員が直接書き込みをしながら話し合いを行ってきましたが、テレワークへの移行に伴い、専用ソフトを導入し、画面共有をしながら書き込みが出来るように対応しました。
一連の変化に対し、特に業務上のコミュニケーションの面において、ベテラン層の社員を中心に根強い不安の声が上がってはきましたが、一度舵を切った以上、社員にはテレワークを前提とした働き方に慣れてもらうしかありません。
そこで、バックオフィスとして最大限のサポートを行い、社員間の「意識格差」を埋めるべく、様々な施策を実践しました。たとえば、テレワークで使用するツールの選定においては、意見に偏りが生じないよう、幅広い年齢・性別の社員からテスターを募り、現場の意見を尊重しました。また、ツールのマニュアルについても、ページ数が多く、目を通してもらうことが期待できないものについては、業務で最低限必要な機能の説明箇所を抽出し、冊子サイズにまで落とし込んだ「社内マニュアル」を作成するとともに、社内システム上でのキーワード検索機能の実装や補足情報の掲載(FAQやQ&A)を行いました。
 テレワークで働く社員の様子
テレワークで働く社員の様子
強制せず、あくまで“サポート”に徹した社内コミュケーションの推進
当社は業務の性質上、技術的な側面が強いため、業務で関わりのある部署間のコミュニケーションは緊密にとれていますが、テレワークにおいては、関わる頻度が少ない部署との接点が課題となります。そこで、忘年会や新年会、歓送迎会など、「リアルイベント」の開催を希望する社員に対しては、費用を会社が補助しています。
Teams上でのコミュニケーションについても、グループチャットやオンラインゲーム大会の開催など業務時間を超えて行うことがある場合には、社員からの事前申請により許可しています。
当社では社員間のコミュニケーションに対し、強制ではなく、あくまでも“箱”を用意し、サポートに徹するスタンスをとっています。会社が“介入“することによって、コミュニケーションが目的化してしまうことによるストレスなどが生じることを避けるためです。
 社内イベントの様子
社内イベントの様子
将来を見据えた「教育」への注力と「福利厚生」の推進
テレワーク導入から数年が経過する中、当社ではマネジメントにおいて、「知識」と「意識」のレベルでの乖離が生じていることに危機感を感じています。そこで、マネージャー層に対しては、現在の環境に応じたマネジメントに関する「教育」に注力していきます。
また、採用活動において、テレワーク制度だけをアドバンテージとすることには限界が見えつつある中、新入社員に対する新たなロイヤリティとして、さらには既存社員のエンゲージメントの観点からも、今後は「福利厚生」の充実も推進していく予定です。
 オンラインでコミュニケーションを取る社員
オンラインでコミュニケーションを取る社員