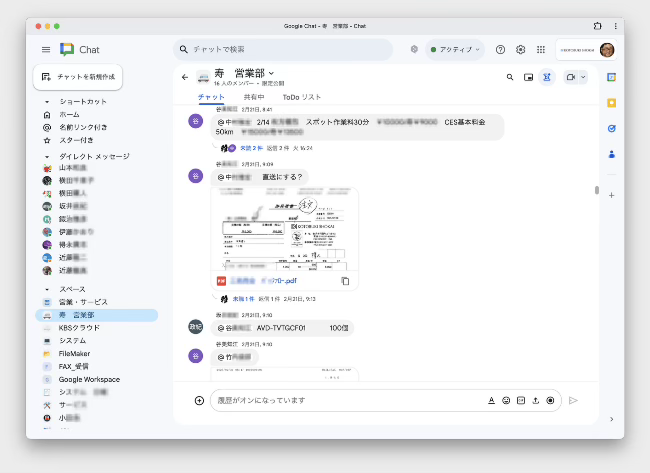株式会社寿商会
2025/03/28
会社概要・業務内容
社名:株式会社寿商会
ホームページURL:https://kotovuki.co.jp/
所在地:(本社)石川県金沢市問屋町2丁目82、(東京事業所)東京都中央区日本橋本町4-1-3
従業員規模:27人
業種:卸売業・小売業、情報通信業
事業内容:システム開発、IT導入コンサルティング、事務機器卸・販売・メンテナンス
残業削減に向けて、移動時間を減らすためにテレワークを導入
当社はシステム開発と事務機器卸売の2つを主要事業としています。システム開発は全国規模で、事務機器卸売は本社のある石川県を中心に展開しています。
テレワークを導入した理由は、働き方改革の一環として残業時間の削減に取り組む必要があると考えたためです。業務フローを大きく変えずに効果を上げやすい部分として、通勤及び顧客訪問に要する移動時間の削減に着目しました。システム部門は出社しなくてもできる業務が中心なのでテレワークしやすいですし、事務機器部門は顧客訪問が多い仕事ではありますが、直行直帰を推奨し、会議もリモート参加を可能とすることで、テレワークができる体制を実現しました。その結果、移動時間を大きく削減できたほか、移動の合間の空き時間も活用できるようになり、平均残業時間は20%以上削減されました。
 オフィス外観
オフィス外観
事業間および新入社員とのコミュニケーション不足を解消する工夫
テレワーク導入から1年ほど経過した頃、コミュニケーション不足の解消が課題として浮上しました。事務機器事業では、もともとコピー機や机といったハードウェアの提供が中心でしたが、時代の変化に伴い、クラウドサービスの提案なども求められるようになっていました。そのため、システム事業で培ったノウハウを事務機器事業でも活かせるよう、両者の連携をより強化する必要がありました。
この課題を解決するため、令和4年にオフィスの建て替えを実施しました。以前のオフィスは仕事に集中できる環境を重視していましたが、新オフィスではカフェコーナーやテラス、仕切りのないオープンなスペースを設け、会話のしやすさを意識しました。また、週に一度の出社曜日を定め、事業間の交流を促進しています。
もうひとつの課題は、新入社員との交流や教育です。テレワーク下では新入社員の教育機会が減り、孤立感も生じやすくなります。対策として、現在は毎朝30分間、中堅以上の社員とオンラインで雑談会を実施し、コミュニケーションの機会を増やしています。また、新卒入社の社員は一定期間毎日出社し、電話対応や来客対応を通じて社会人としての基礎を学びつつ、業務に慣れてもらうようにしています。
 新オフィスの様子
新オフィスの様子
マネジメントのコツはグループチャット使用ルールの明確化
テレワーク体制になってからも、マネジメント上の大きな問題は発生していません。その要因は、グループチャットを有効活用できていることだと思います。当社では、同じオフィスにいる相手とも基本的にチャットで会話をしています。またその際、1対1のやりとりではなく、グループチャット内で会話するよう呼びかけています。これにより、他の社員も会話を目にすることができ、結果的にグループ内での報告・情報共有が促進されます。会話の内容から、発生しうる問題をマネジャー層が早期に察知し、対応できるメリットもあります。
オフィス勤務時には、自然と耳に入る周囲の会話から業務を学んだり、問題に気づくことができますが、当社では同じことをグループチャット上で実現できています。ただし、チャットが飛び交いすぎると確認が大変になるため、「話しかけたい相手にはメンションをつける」などのルールを徹底し、負担を減らす工夫もしています。
デジタルツールの導入をスムーズに受け入れられるのは若い社員だけだと思う人もいるかもしれませんが、当社の社員は50代がメインで、全員がグループチャットをうまく使いこなしています。ツールの利用ルールを明確にして、利便性やメリットを理解してもらえれば、テレワークを浸透させることは難しくないと思います。
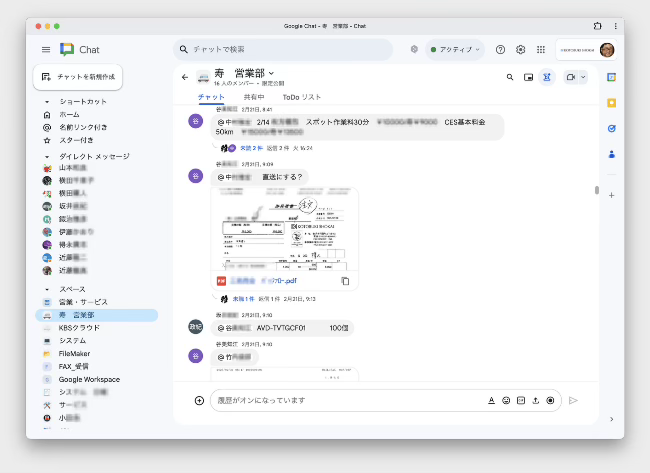 グループチャットの画面
グループチャットの画面
社員の働きやすさや満足度もテレワーク導入後に大きく向上
テレワーク導入後は残業時間だけでなく、通勤や移動にかかる旅費交通費を71%、ガソリン代などの燃料費を23%削減できています。また、社員アンケートでは「仕事のしやすさ」「満足度」に関して、10点中8~10点と回答する社員が大幅に増えました。社長の立場からは、社員と1対1で話しやすいという利点も感じています。オフィスで社長室に呼び出されたら緊張してしまうと思いますが、今は「ウェブ会議で少し話そうか」といったように、気軽な会話ができるようになりました。
今後の課題としては、対顧客の業務効率化が挙げられます。社内の効率化はある程度成功したものの、顧客とのコミュニケーションの取り方や業務遂行の方法については、まだ改善の余地があります。クラウドツールなどを活用しながら、より効率的な業務プロセスを構築していくことが、今後の重要な取り組みになると考えています。